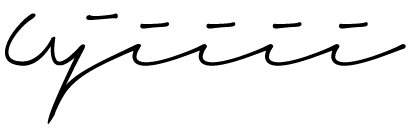SEE EVERYTHING ONCE / TRIP TO SOUTHERN DAY35
ルート66がかつて人々によって今よりもずっと使われていた頃、スティーブン・ショアがローライ35一つを持ってその道を旅していた頃かそれよりももっと前。ルート66を走っていると、その当時の趣はおそらくもう残っていないのではないかと思ってしまう瞬間が度々ある。これは自分のエゴであることは承知しているのだけれど、当時の面影が「残されている」と思える街は観光地化され、文化的な遺産として保存されているように感じられてしまう。それは跡形もなく場所自体が消されてしまっていることよりは100万倍くらいいいし、それだけでも特筆すべき、賞賛すべきことなのだけれど、町と町との間に突如として現れる「本当の手付かずの場所」を見てしまうと、敢えて人が手を入れて何かを残すということの価値が霞んでしまうように思えてしまう。アーリントン、その日朝起きて最初についた街は地図上でも道路がつながっていることがわからないくらい小さな辺境の街だった。ほぼほぼ街は廃村になっていたが、奥に車で進んでいくと家が5.6件連なる小さな集落があった。街の入口には小さなモーテルが古びたサインを掲げて営業を続けていた。朝の冷たい空気と黄金色に輝く枯れた牧草の中に佇むそのモーテルは、昔から誰も知らない場所で時を刻み続けていた。モーテルへと続く道は倒木によって塞がれていたので、その前に車を停めて辺りの様子を伺いに行った。この日は天気も良くいい風が吹いていた。敢えて薄着で外に出てその風の冷たさを感じると眼が冴えてこの日一日も旅を続けられそうな気がした。今、僕はアメリカ中部のミズーリ州からオクラホマ州に向かうルート66の上にいた。旅はあと10日で終わる予定だった。ここからあと何マイル走ればポートランドに戻れるのかわからなかったけれど、とにかく旅は距離的にも時間的にも残り1/4ほどまでに減っていた。この日の最終目的地はタルサというオクラホマ州に東部の街、ラリー・クラークの有名な写真集が撮られた街だった。
小さな街のガソリンスタンドで休んでいると、なぜか分からないけれど猫が擦り寄ってくることがままある。トラックドライバーや旅行者が餌付けをしているのでそれになれてしまっていたのだろうが、このドリトルという街のガソリンスタンドでは僕に向かってたくさんの猫がにじり寄ってきた。その次に立ち寄ったドンと言う街の大きな交差点にあるガソリンスタンドでもそうだった。一人で旅を続けていると、こうした人間でない生き物とのかかわり合いでさえ貴重なものに思えてくるのは不思議だった。お腹を見せて寝転ぶ猫を適度に撫で回し(猫アレルギーなのであまり触れない、、!)、ビスケットの破片やビーフジャーキーの切れ端をあげると喜んで食べていた。キオスクのおばちゃんがこちらを見ながら微笑んでいたので話しかけて猫のことを聞いてみたら、どうやらこの猫はどこから来たのかわからない野良猫だと言っていた。昼下がりの陽気な気候の中、日向ぼっこをしながらこんな広大な景色を見ながら暮らしていける猫は世界を探してもそうはいないだろうと思う。僕が車に戻ろうとすると後ろをずっと追いかけてきた。車のドアを締めてエンジンをふかしても、どうやら車から離れていなくて、車を動かしてひいてしまっては大変だということで、ドアを開けて猫の位置を確認しながらゆっくりと車を動かした。僕がスタンドの出口の辺りまでいくと猫はゆっくりとキオスクのほうに歩いていき、ドアの前の定位置のところに座って、そのまま寝転んでいた。
フェアグローブという街を通り過ぎた時に気になる看板を見つけた。「ヒルビリースピードレース」と書かれた古ぼけた看板が妙に気になり、きた道をUターンしてその看板の指し示す方へと向かった。ヒルビリースピードレースの会場は広大な敷地にボロボロの車が丁寧に並べてあり、その奥にはレース用のトラックと観客席がちょうど陸上競技場のような形で設置されていた。あいにく今日はその「スピードレース」はやっていなくて、中には誰もいないように見えた。しかしレース場のゲートは開いていたので意を決して中に入ってみた。僕がカメラを持って錆びついたトラクターや消防車など、並べて置かれてある車達の写真を撮っていると奥の方から大きな軍用車のような車に乗ったいかにも元軍人といった出で立ちの初老の男性が出てきた。勝手に入ってしまったし、これは何か怒られるかもしれないと内心諦めていたが彼の反応は予想とは正反対だった。「やあこんにちは、僕の名前はホッジスと言うんだ、君は?」と気さくに会話を始めてくれたと思ったら、そこらじゅうに停まっている錆た車や作業マシンの解説を勝手に始めた。「この車は1940年製で、、、この消防車はこの州で昔使われていたモデルなんだ、、、blablabla…」彼の解説は留まるところを知らず気づけば30分以上もの間レース場に置いてある車について説明していた。そのうちの車の中の1台に「Trump, I’m back!」と書かれたボロボロに焼け落ちた車を見つけたがあれはいったいなんだったのだろうか。そうしているうちにホッジスさんが飼いならしていると思われるドでかいドーベルマンのような犬がこっちに向かって全力で走ってきては吠え立てるので、居ても立ってもいられないとその場をあとにした。いったいこのレース場はなんだったのだろう。
タルサについたころにはもう夜になっていて、道路沿いに見つけたサブウェイで大きなサンドイッチを注文して車の中で食べながら見ていた。タルサの街は予想よりもかなり大きく、少なくともここ数日で訪れた街の中では一番に大きかった。そしてもっと荒廃した場所なのかと思いきや、見た目上はいたって普通の街のように見えた。車の中でサンドイッチを食べながら「KIDS」を見ていた。この映画を見るのは何年ぶりだろうというくらいに久しぶりだった。ざらついた粒子が目立つ画面、そしていきなり始まる幼い男女のセックスシーンは相変わらず背徳感を伴った美しさと衝撃があった。当時のことを思い返すと、そもそもこの映画がラリー・クラークの撮った映画であることを知らず、KIDSのサウンドトラックの最後の曲、Slintの「Good Morning, Captain」からこの映画のことを知っただけで何の気なしにただ見ていたように思う。単純にこの時聴いたこのSlintの「Good Morning, Captain」が当時の自分にとっては格好が良すぎたということもあるのだけれど、繰り返し聴いていたこのサウンドトラックによってSlintもFolk ImprosionもSebadohも好きになったし(今でも「KIDS」のサウンドトラックは映画音楽の中でもかなり好きな方)、自分の音楽の世界観を広げてくれた大きな要因の一つだった。こと映画についてはアメリカでよくある少年たちの堕落した人生は脚色された非現実的な風景、つまるところフィクションだと思っていた節があった。あまりにも自分からかけ離れていたし、突きつけられる事実が重すぎるというか現実に起きうることだと信じ難かった。可能性としてはどこかしらで起きうることだし、実際に起きているのだろうけれど感覚と理解が乖離しているような気がしていた。その後、写真に興味を持ち始めた跡に『タルサ』と題された写真集を見つけたことでその考え方は大きく変わった。ラリー・クラークがKIDSに出てきたような、危うさに染まる少年や少女達を執拗にフィルムに収め続けていたこと。そしていつか写真美術館で見た「ラヴズ・ボディ展」で見た窓際で暖かい光を浴びる十代の妊婦も彼によって撮られたものであること。彼の写真家としての生き方がその頃より一貫していたこと(映画についてはちょっと何とも言えないが)。KIDSのサウンドトラックに入っていたセバドーの「Spoiled」を繰り返し聞くうちに、「KIDS」という映画がハーモニー・コリンによって脚本が書かれていることを考慮したとしても、おそらくラリー・クラークの見てきた風景と相違ないのではないかと思うようになった。改めてこの映画をタルサのガソリンスタンドの駐車場で、iPhoneの小さな画面で見返していた時(映画の中に映るニューヨークの町並みとタルサの町並みに違いはあれど)おそらくはこの町でも同じようなことがかつて起きていて、そして今でも見えない場所で起きているのではないかというリアリティがあった。雨で濡れる車の窓から雑多なネオンがきらめいて見える度に、何か得体の知らないじっとりとした恐怖がどこかしらに潜んでいそうな気がして怖かった。自分がかつて何の気なしに好きだった破滅的な音楽や映像が質量を持って迫ってきているような気がしていた。モーテルを探す途中に立ち寄ったある郊外で、ふらつきながら歩く若者が近づいてきて僕に言った。「こんなのはいるかい?」手にはどこかで見覚えがありそうな透明の袋が握られていた。正直なところ非常に怖かったけれど「僕はクリーンでいることにしているんだ、夜を楽しんでね」と伝えてすぐにその場を立ち去った。